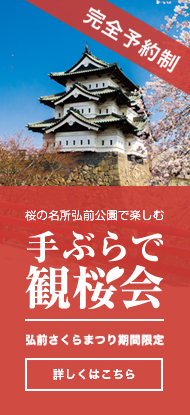その名は玄武という亀に由来

外濠を隔て、市街地である亀甲町と四の丸に架かります。四神相応の地(※1)にならい、城外北方にある土地を亀甲町、北門を亀甲門と定めたことから、この橋もまた亀甲橋となったと思われます。
藩政時代は、戦になると敵の侵入を防ぐため壊される架け橋でした。
※1 四神相応の地とは、風水思想でいう、東に青龍が宿る川、西に白虎が宿る道、南に朱雀が宿る池、北に玄武が宿る山に囲まれた土地をいいます。
玄武は脚の長い亀に、蛇が巻き付いた形で表現されます。

橋の周辺
亀甲橋の付近には、江戸後期に建築されたという石場家住宅が、その奥の仲町には武家屋敷があります。周辺の外濠では、フナを釣る市民の姿がよく見られます。
基本情報
| 架け替え | 2004年(平成16年)3月 |
|---|---|
| 橋の長さ | 14.4メートル |
| 橋の幅 | 4.5メートル |
位置
より大きな地図で 亀甲橋 を表示
写真でみる
亀甲町へ
亀甲橋を渡ると正面に広がるのは、亀甲町。門や橋と同じく「亀甲」の名を冠していることからわかるように、城下町弘前の中でももっとも古い歴史を持つ町のひとつです。

緑の橋とのコントラスト
優美な姿を見せる亀甲橋。春には桜が、秋にはもみじが周囲に咲き誇り、落ち着いた緑の橋とのコントラストが絶妙な美しさを演出してくれます。

津軽藩ねぷた村
亀甲橋の上から、外濠を眺めた様子。濠のさらに向こうに見える建物は、津軽藩ねぷた村です。お土産売り場やお食事どころ、大きな駐車場も備えており、この付近から弘前公園一帯を散策する拠点のひとつによいでしょう。
なお、濠沿いの道路(県道31号線)は道幅が狭いわりに交通量が激しいので、徒歩での移動はご注意ください。
周辺施設・スポット
亀甲門/北門
築城後間もなくこの門が弘前城の正門とされていましたが、やがて追手門が正門となり、北門は裏門の扱いとなりました。
詳しく見る
護国神社
護国神社は、12代藩主
詳しく見る

レクリエーション広場
広場を取り囲むように、ソメイヨシノが植えられており、春は優雅な花弁の舞を楽しむことができます。
詳しく見る
賀田橋
二階堰を隔て、三の丸と四の丸に架かります。戦になると敵の侵入を防ぐため壊される架け橋でした。
詳しく見る
最寄りの出口

亀甲門口
外濠に架かる橋は「
北門口の付近には路線バスがあり、また周辺には1回300円~500円の駐車場があるため、車で来場される方にも便利です。
最寄のトイレ
より大きな地図で 亀甲門(北門)前トイレ を表示
亀甲門(北門)前トイレ
亀甲門(北門)をくぐり園内に入ると、すぐ左手の方向にあります。
トイレの標識は、人々に解りやすい標識でありながら、公園の景観を損なわないデザインになっております。