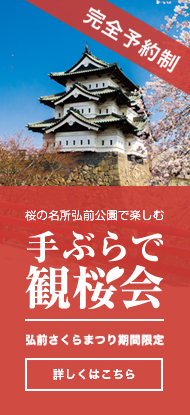弘前ねぷたまつりについて
弘前ねぷたまつりは国の重要無形民俗文化財に指定されています。毎年8月1日~7日まで開催され、県内外から多くの観光客や市民が訪れます。人形の形である「組ねぷた」や「扇ねぷた」が弘前市内を運行します。囃子や太鼓、掛け声とともに、弘前の熱い夜を彩ります。
7日目は「なぬか日」と呼ばれ、河川敷でねぷたを燃やすフィナーレを行います。
弘前ねぷたまつり開催情報
| 開催期間 | 毎年 8月1日~8月7日 通年でねぷたが展示されている施設はこちら |
|---|---|
| 運行コース | 8月1日~8月4日 19:00~ 土手町コース(桜大通りから出発) |
| 8月5日~8月6日 19:00~ 駅前コース(代官町みちのく銀行前から出発) |
|
| 8月7日(なぬか日) 10:00~ 土手町コース(松森町ふれあい広場交差点から出発) |
|
| お問い合わせ先 | 弘前観光コンベンション協会(弘前市立観光館内) TEL:0172-35-3131 |
弘前ねぷたまつりの様子を写真でみる
弘前ねぷたまつりの歴史
 ねぷたまつりの始まりは、もともとは「禊ぎ祓い」という、汚れなどを形代に託し、水に流すお祓いから派生したものだといわれています。
ねぷたまつりの始まりは、もともとは「禊ぎ祓い」という、汚れなどを形代に託し、水に流すお祓いから派生したものだといわれています。
ねぷたの由来には諸説ありますが、その中でも定説なのが「江戸時代に七夕祭の松明流しや精霊流し、盆燈籠などが変化したもの」とされています。
ねぷたが記録されている最も古い書物が1722(享保7)年の「御国日記」で、5代藩主である津軽信寿が「祢むた流」をご高覧した、と記されています。
ねぷたの形

始まりが灯籠流し
始まりが灯籠流しなどであったことから、初期のねぷたは人形や扇の形ではありませんでした。
箱型だったねぷたの形が変わり始めたのが江戸時代後期。弘前が4万5千石から10万石にまで昇格したのをきっかけに、ねぷた灯籠の大型化・人形化が行われました。
それから徐々に飾りがつき、時代とともにねぷたは華やかさを増していきます。
人形の形である「組ねぷた」が現代の形となり、「扇ねぷた」が登場したのが明治から大正にかけて。
弘前の藩祖・津軽為信の幼名である「扇丸」と、ねぷたの台座を応用した新しい作り方で扇型のねぷたが生まれました。
弘前では明治維新で混乱に陥るなか、組ねぷたほど経費も手間もかからない、斬新でユニークな扇ねぷたが主役の座を占めていきました。